■トリエンナーレ終了後の横浜美術館ではじまった次の企画展は日本画家である松井冬子の大規模な個展。フライヤーやポスターなどの展覧会のメインビジュアルに使われている作品は「世界中の子と友達になれる」。藤棚と思しき無数の藤の房が下がる中を少女が歩いている。あまり怖いイメージがなくて意外な気がした。松井冬子の描く絵は静かに刺さるような印象がある、という先入観があったのですが。
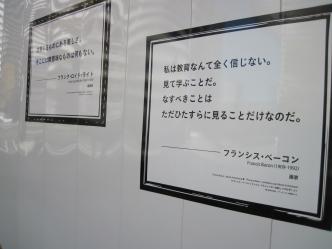
もっとも会場に入ってみれば、思っていた通りの作品が並ぶ。「世界中の子と友達になれる」は松井冬子の藝大卒制作品で、展覧会のビジュアルでは細部がつぶれていてよく見えない。藤棚のような下で少女が歩いている、という説明は間違っていないが、細部が見えてくると穏やかな雰囲気は消え失せ、狂気を孕んだ緊張感を覚えずにはいられない。
はだしの足には血が滲み、その目はうつろの画面の外を見やり、空のゆりかごは何かの喪失があったことを案じさせる。藤の房には蜂が遊弋し、黒い。ここには何か期待させるものがない。あるのは喪失と痛み。

「世界中の子と友達になれる」という松井の言葉は、彼女が幼少の頃に覚えた感覚を下敷きにしている。しかし、言うまでもなく、この類の言葉は綾として使われるのが大抵であり、実現しないことを誰もが知っている。子供の頃に覚えた文字通り「世界中の子と友達になれる」感覚は幼年期によく見られる万能感に基づくであり、年を重ねるうちに忘れてしまう。しかし、その期待に満ちた感覚は実現しないことが理解されるが、感覚は残る。そのギャップは妄執として澱のように心の奥底に蓄積していく。その重みに耐え切れないとき、人は自傷するか、狂気へ陥り心を守るしかなくなる。

松井冬子が描くのはその「妄執」であり、表には見えてこない整理もつかずにのたうつ情念を象徴する要素をちりばめ画面を構成する。それはフリークな犬であったり、幽霊であったりする。それは松井冬子が見ているリアルであり、たいがいの人はあえて見ない風景。澱として溜め込まれた痛みや狂気を仮託したシンボルを計算して構成された画面は静かで緊張感に満ち、一目見れば忘れられない強い印象を残す。

横浜美術館の常設には日本画の専門室もあり、そちらのトーンのゆるさにほっとする。


