■二日目。岡崎会場は一応駆け足ながらも見終えているので、名古屋市内の会場のみ。白川、栄をまわり、長者町を最後にしようと思った。帰りの時間が決まっているので、長者町を最後にもってくると時間調整がやりやすいのではないかという思惑があった。
白川には名古屋市美術館があって、ここが会場になっている。前回は塩田千春の大型インスタレーションが展示されてとても印象に強かったのだけど、今回は市美の建築物そのものを作品とするコンセプトのようで、作品展示数そのものはあまり多くはなかった。



市美の展示では1Fにあるアルフレッド・ジャーの「黒板プロジェクト」が少し沁みた。大量のチョーク、黒板に「生ましめんかな」の言葉が投影される。福島の洪水に洗われた小学校を連想せずにはいられない。ただ、この言葉が投影されるまでの間隔がやたらと長く、ちょっと間が持たなかった。
面白かったのは2Fの杉戸博の作品で、美術館の動線を変更する試み、らしい。合成繊維で織られた網で空間を仕切られていて、正直安っぽく目には映るのだけど、写真を撮ってみたらあら不思議、ちょっと宗教的に見えなくもない空間が現れて面白かったです。

白川を後にして、栄へ。若宮大路を東に歩いて矢場町あたりで久屋大通に入る。




栄会場の中心は愛知県芸術センター。

オアシス21をB2まで下がって、芸術センターに入るとヤノベケンジのサンチャイルドがお出迎え。放射線防護服のヘルメットを脱いだサンチャイルドは、福島の事故からの回復を象徴している(と言い切ってしまう)。

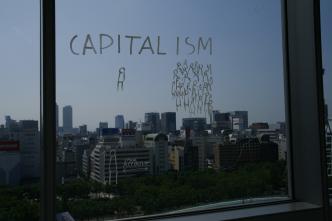
ただ、前日にみた、岡崎・納屋橋に比べるとインパクトは薄いような印象でした。思ったほど密度が濃くない感じがあって、初回の「あれもこれも」という貪欲さが薄い感じが。それと、原発事故にフォーカスしすぎている感じもあって、これも馴染めない一因でした。物語としての原発事故に基づいて作品が作られているのではないかという印象は拭えませんでした。


長者町会場の目玉はナデガタ・インスタント・パーティーの「中部スタジオ」。中部電力の変電施設跡を改装して「中部スタジオ」という架空の映画スタジオの歴史を回顧するという趣向。前回は岡崎の美容室跡のようなサイトスペシフィックな作品が多く展示されていて、観客も多く行き交っていたのですが、今回はさほど多いようにも見えず。



気になるのは街中に入ったサイトスペシフィックな作品が回顧的なものになっていることで、それはとりもなおさずアーティストがその土地において未来を思い描くことができないでいるということではないだろうか。それはアーティストだけでなく、おそらく土地の人々においてもなお、ということではないか。それを描けるようにする力もアートにはあるのではないかと思うのだけど。



